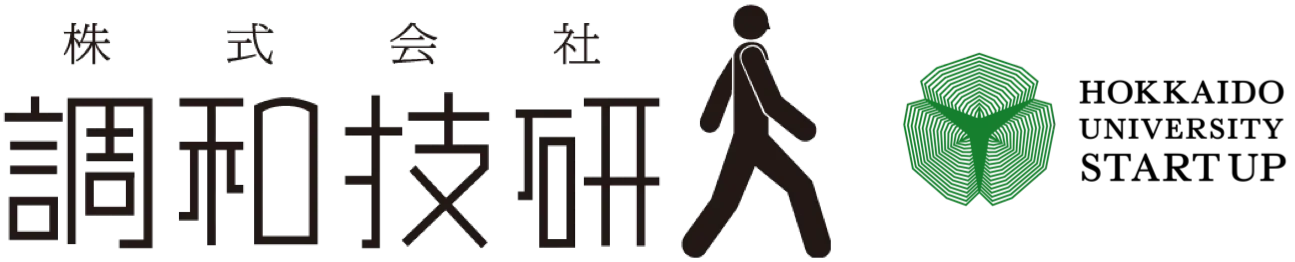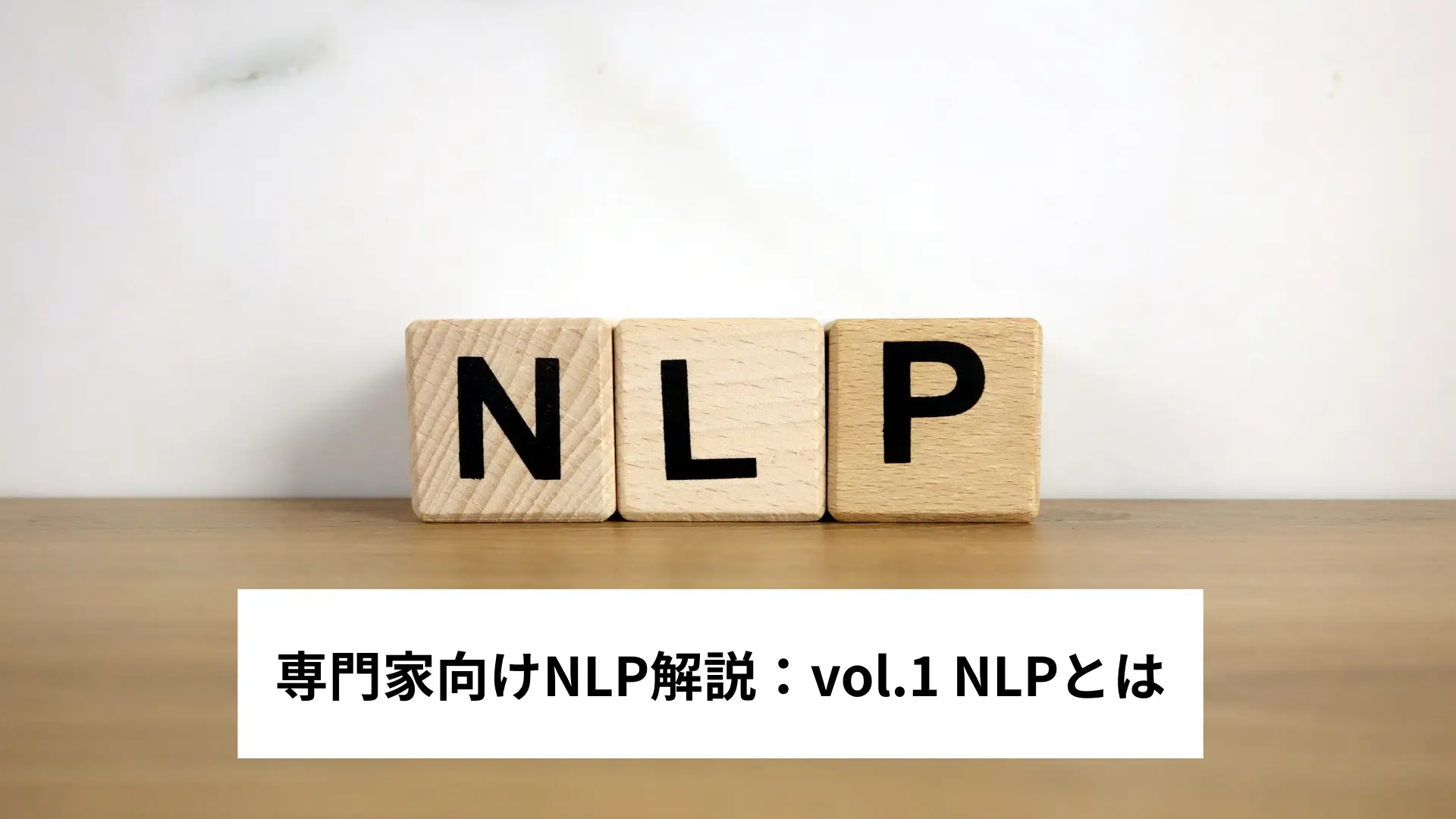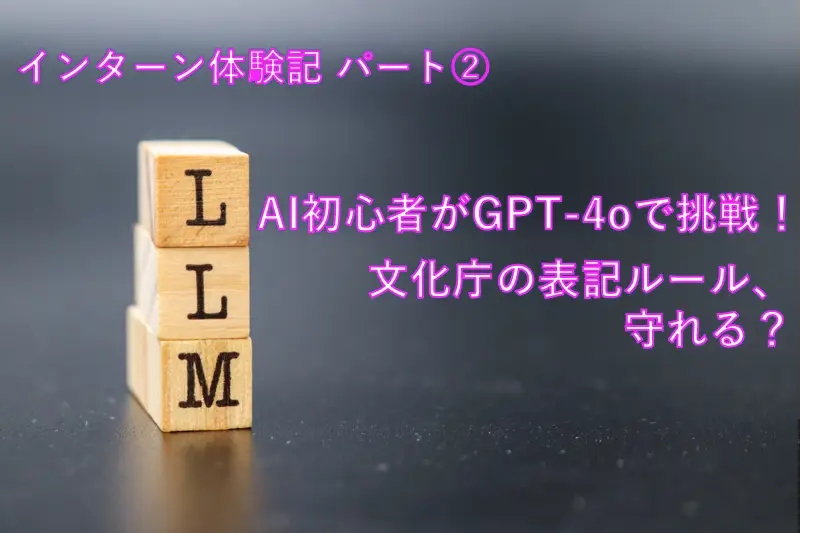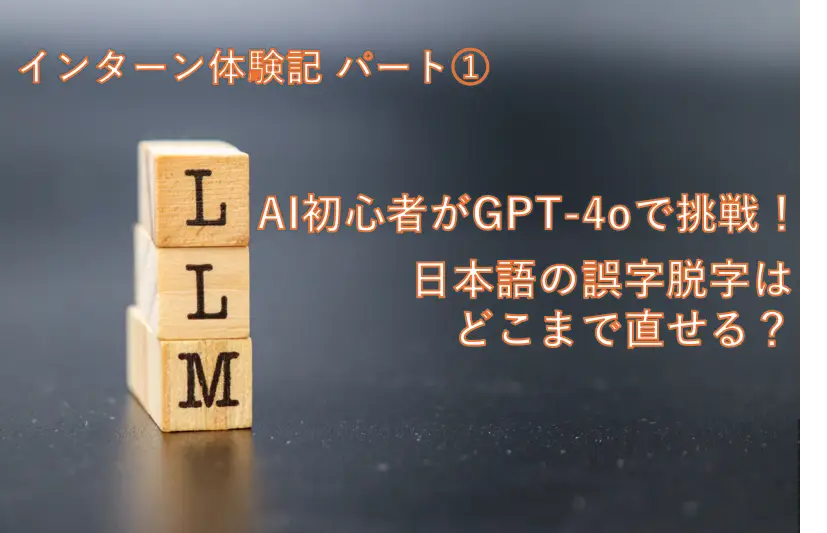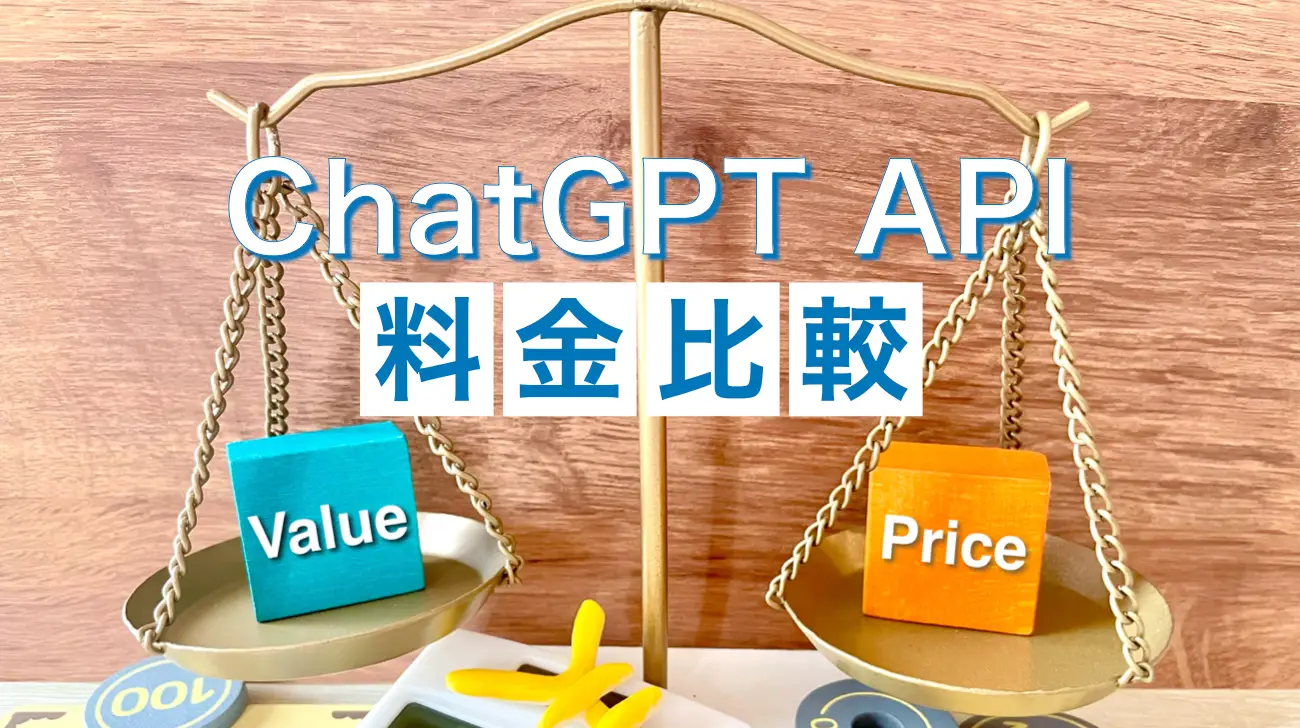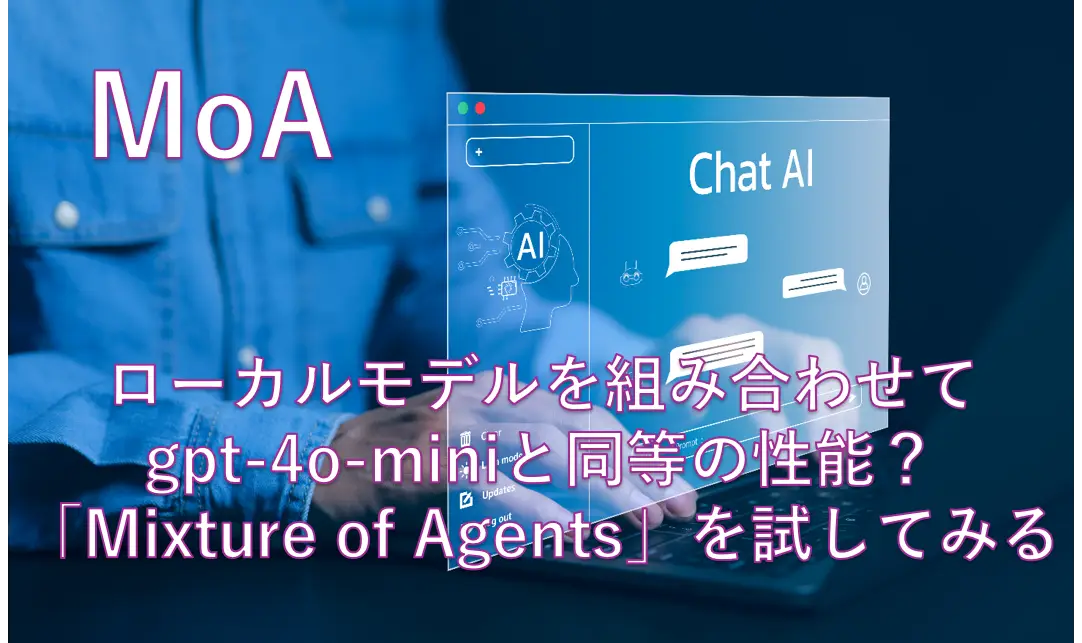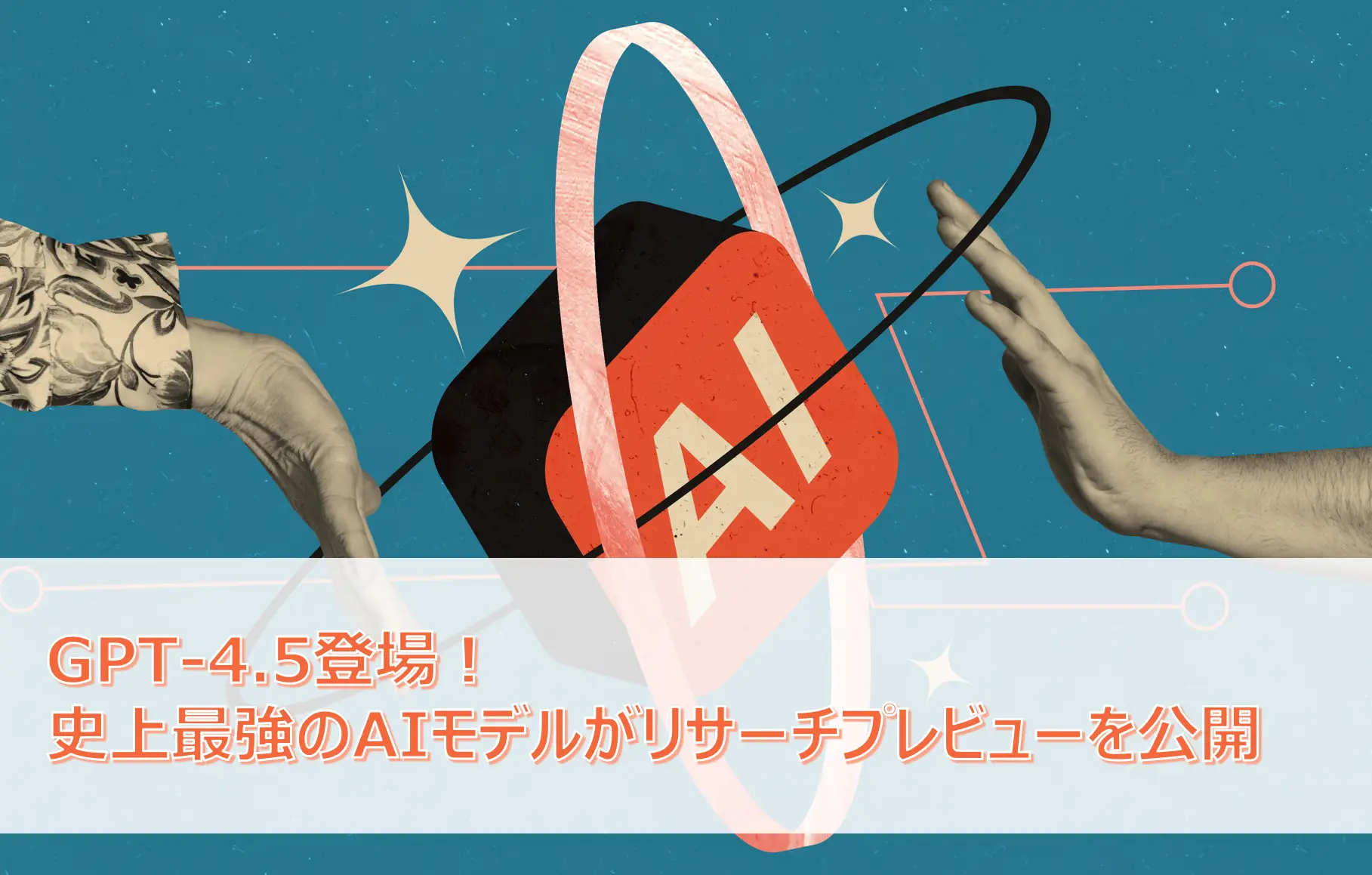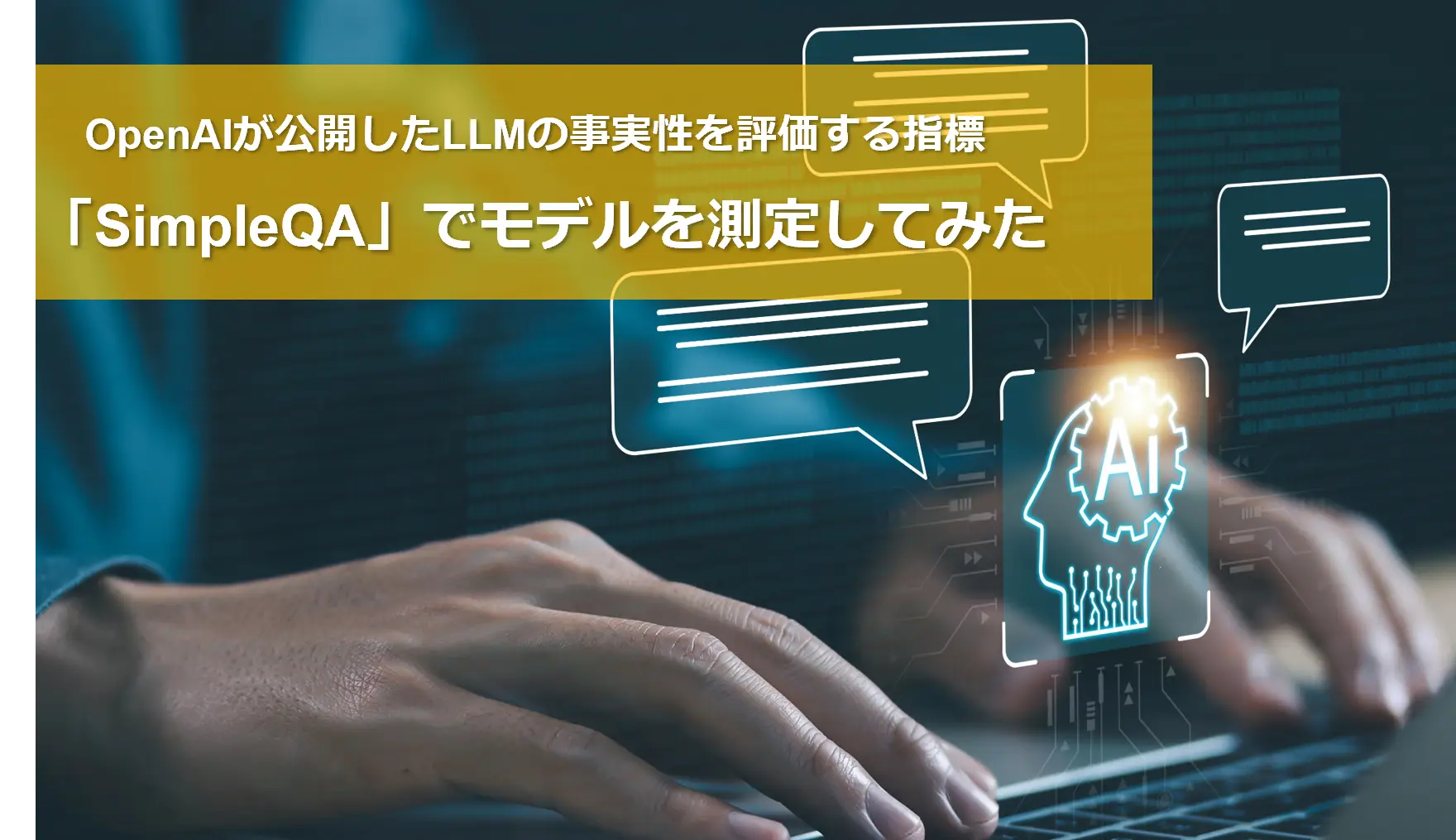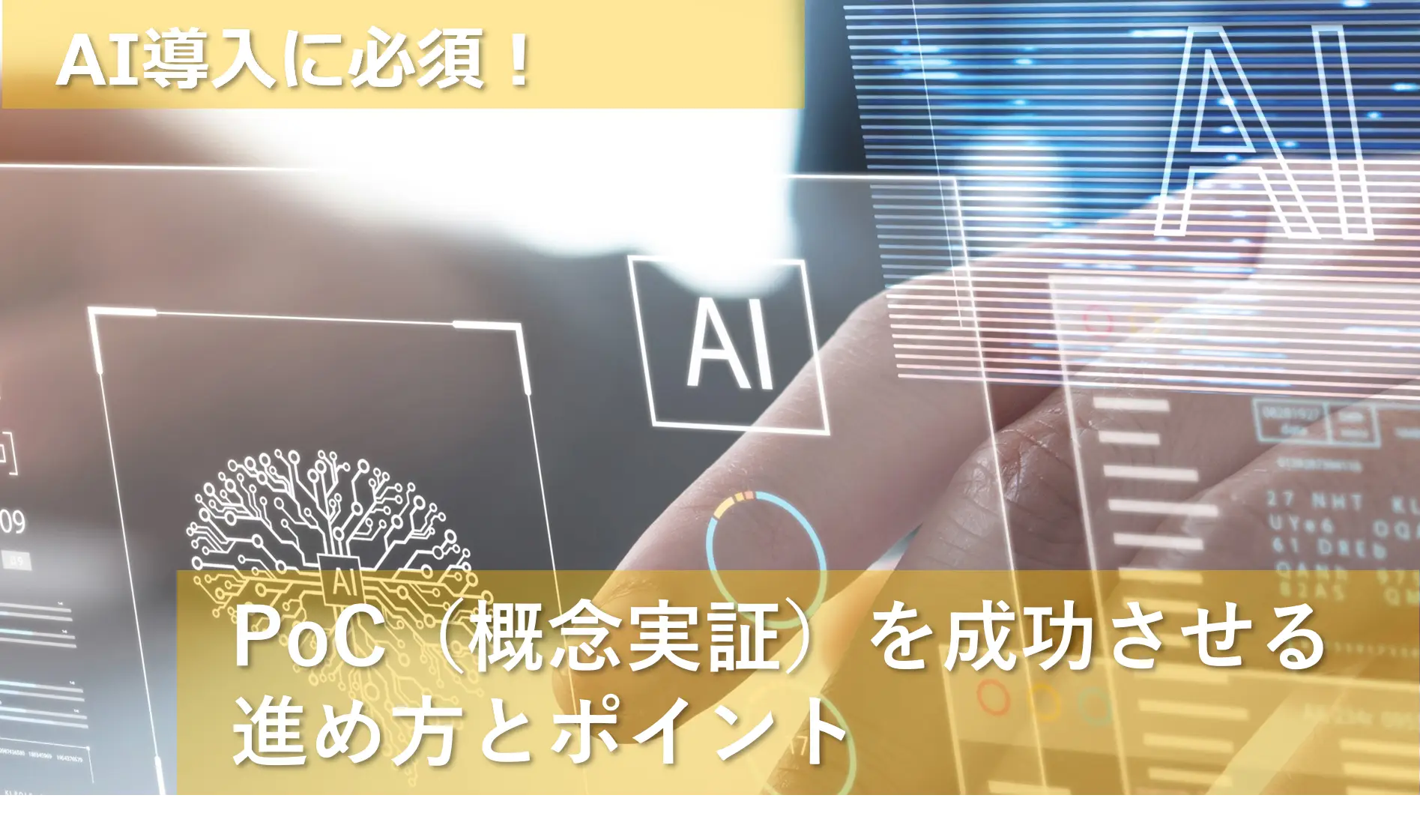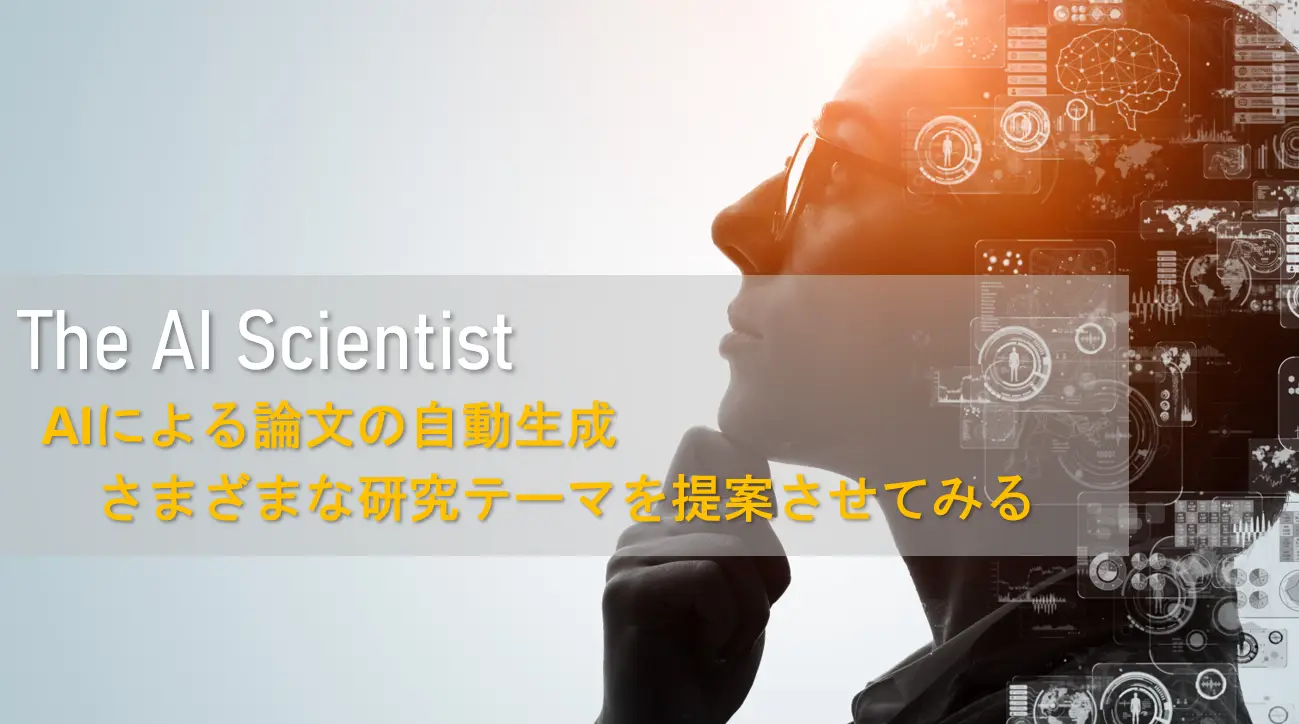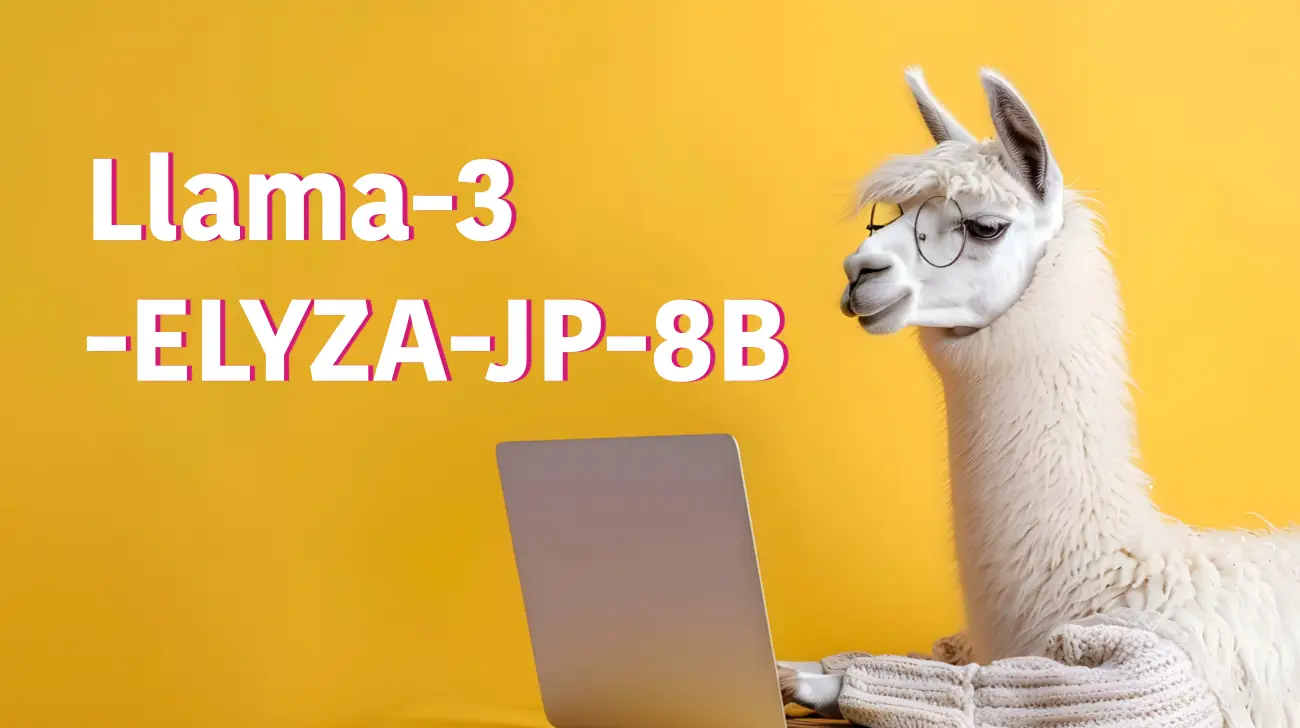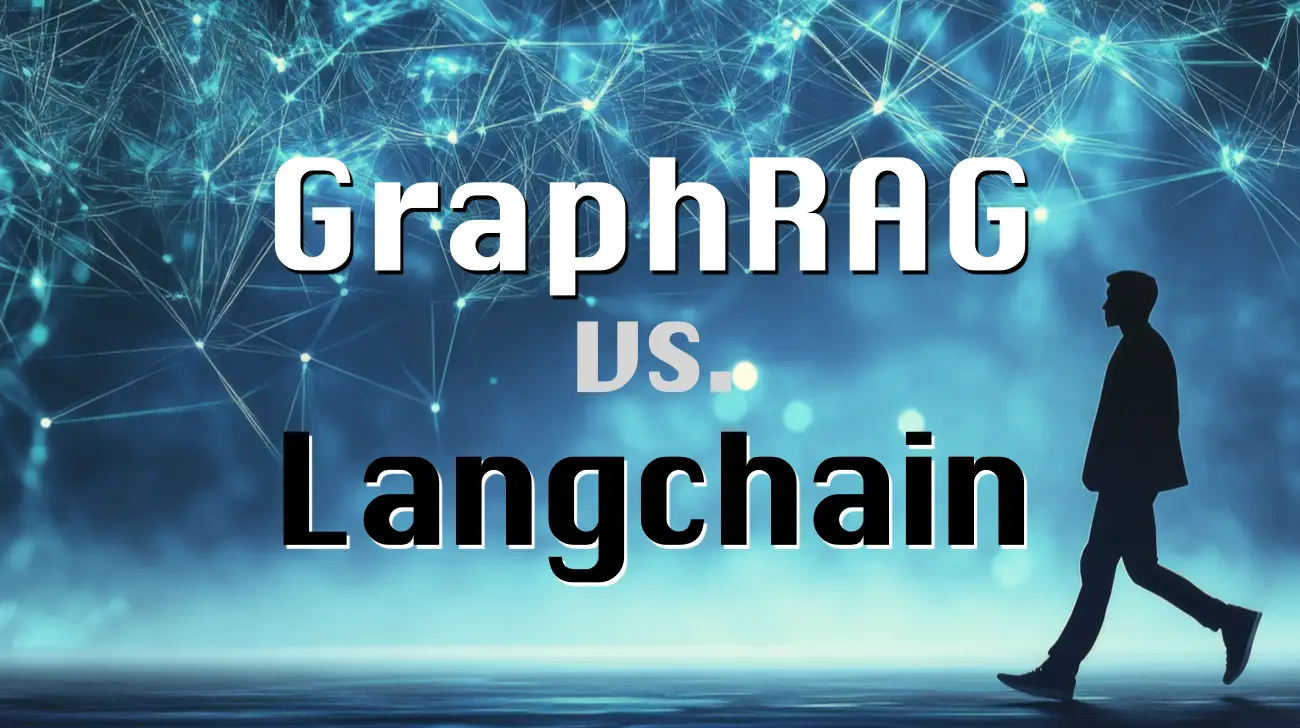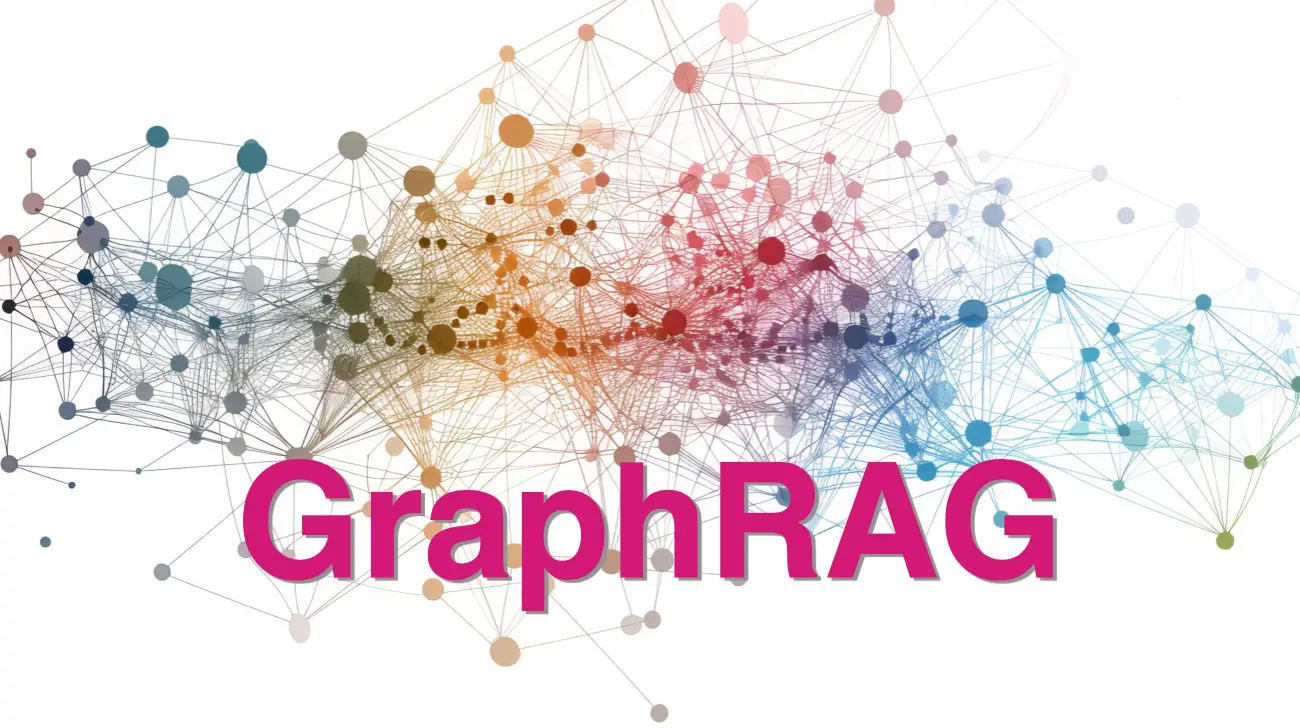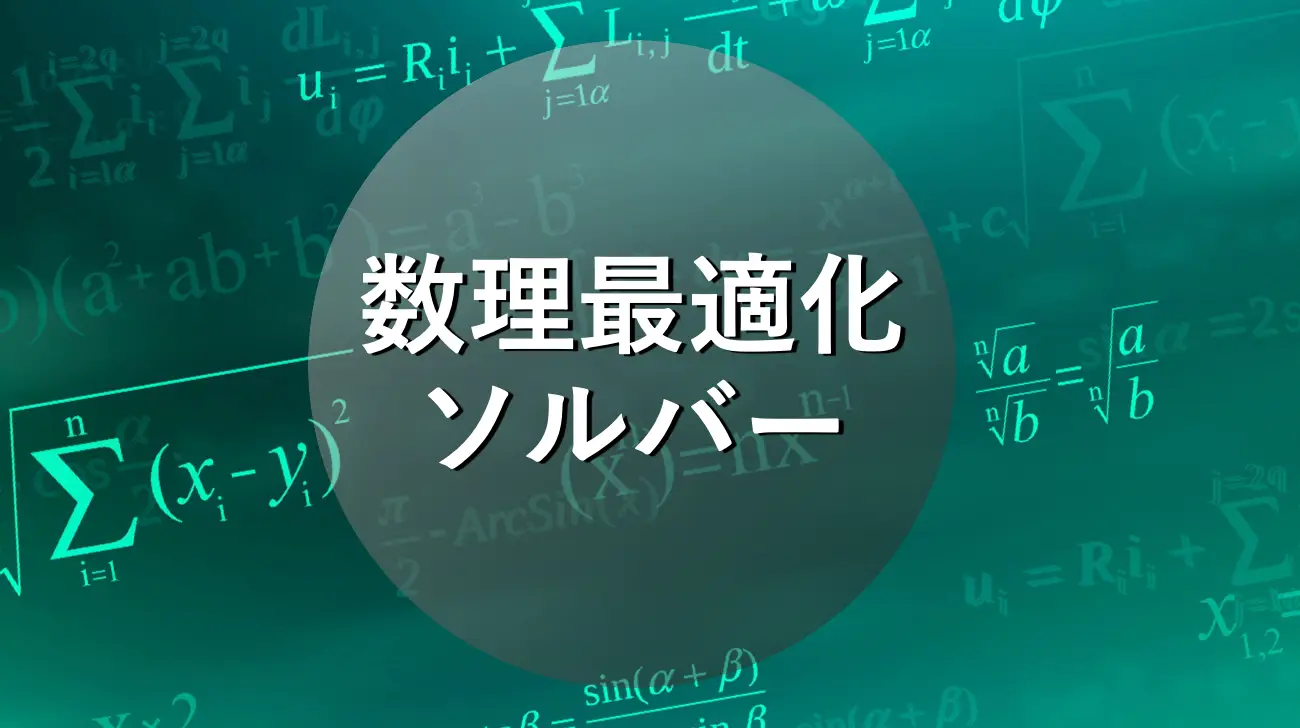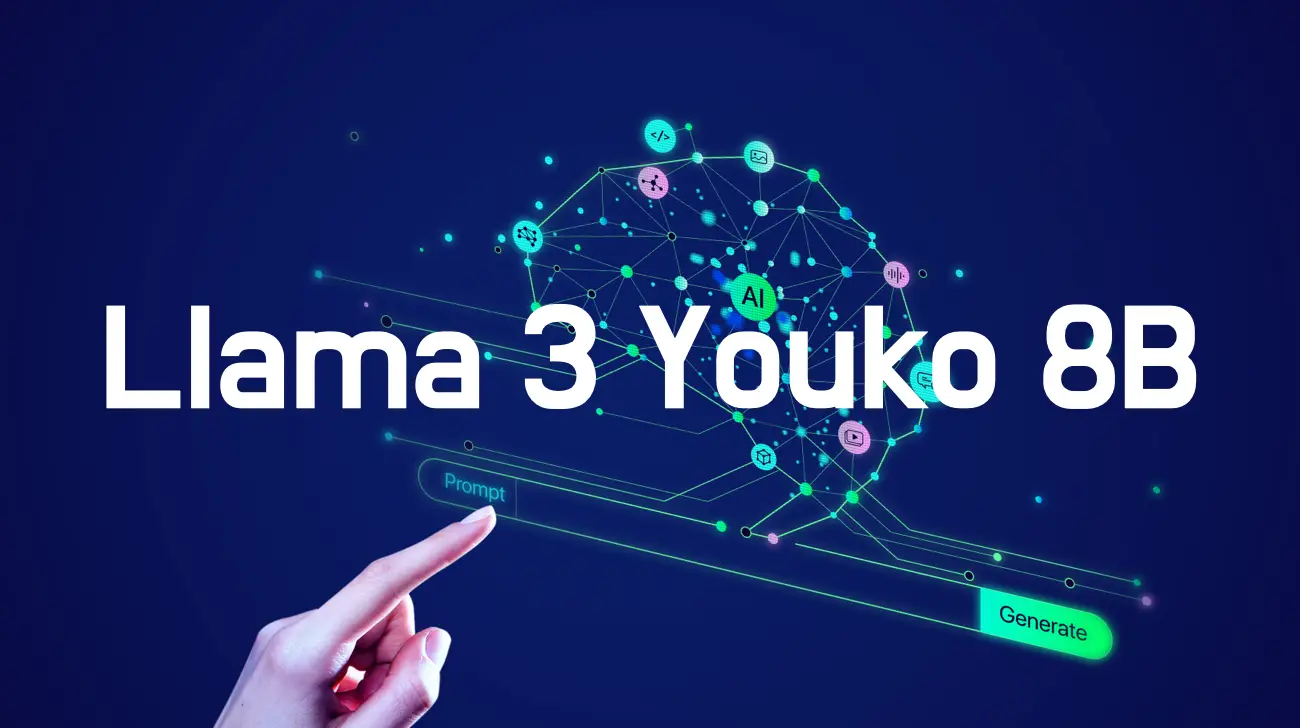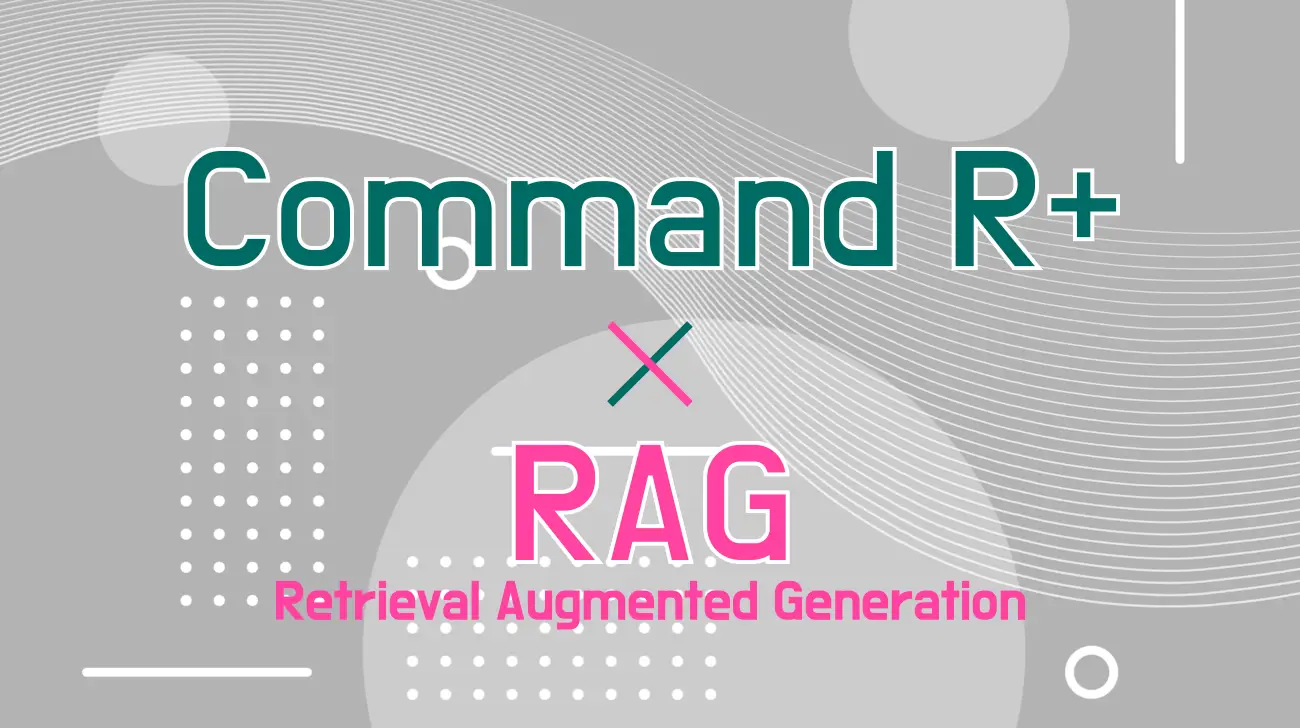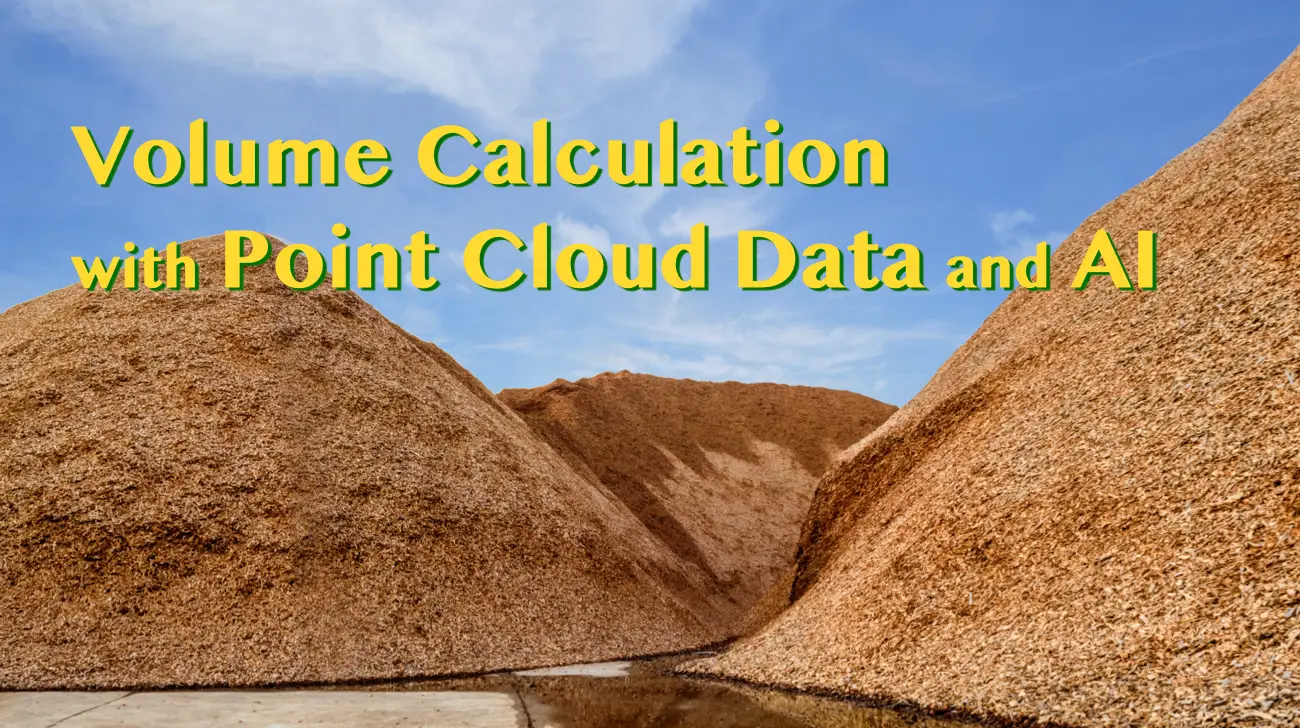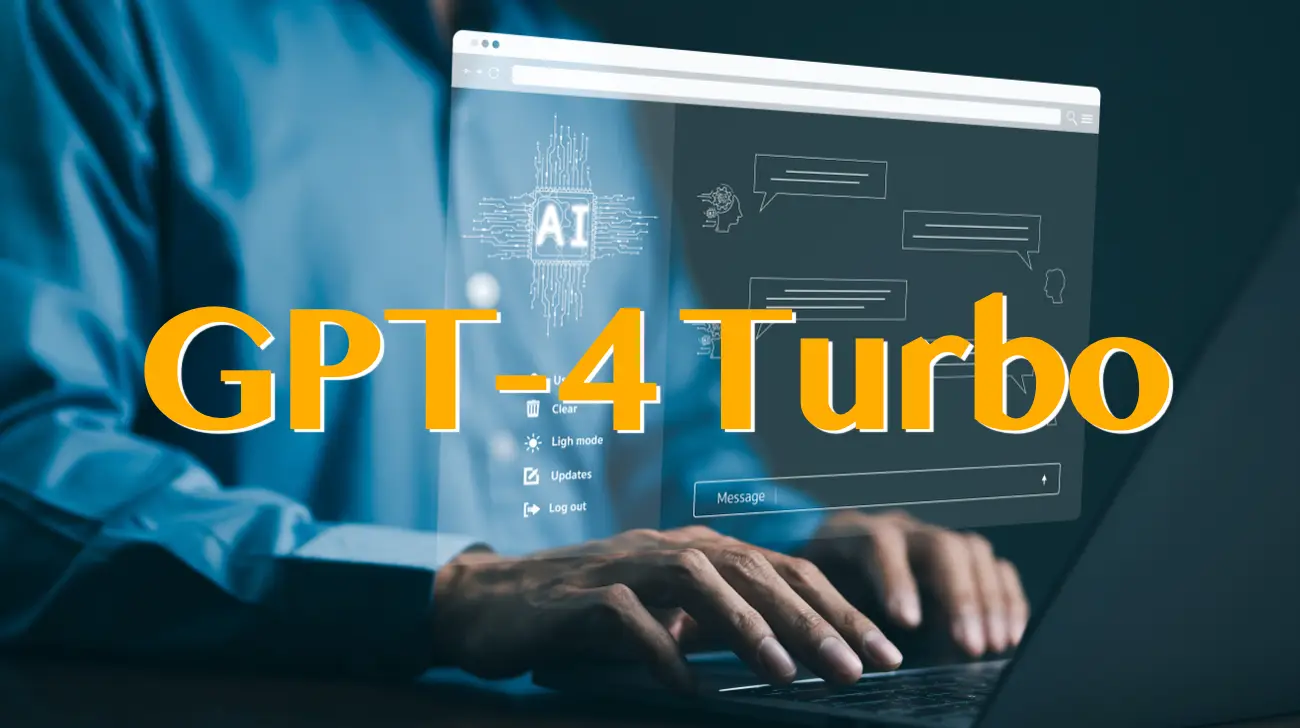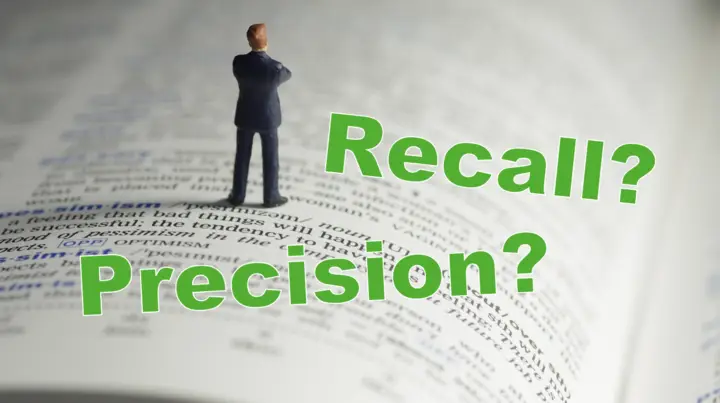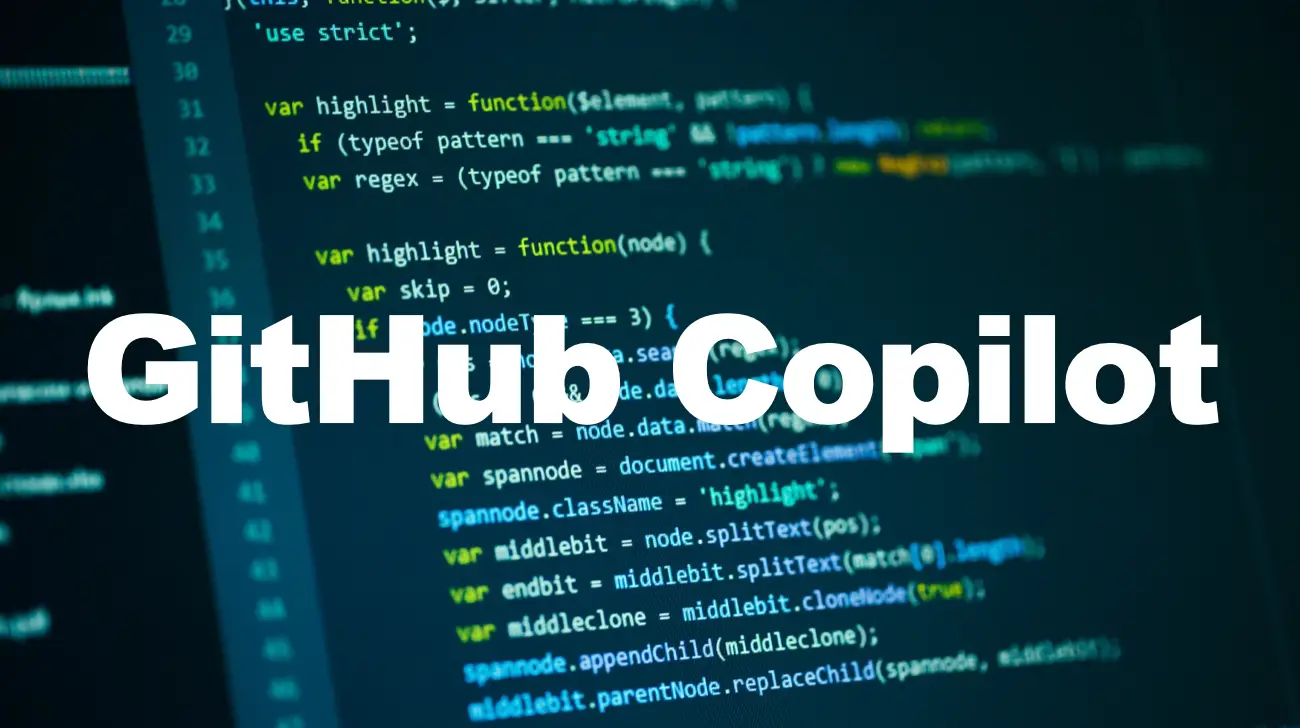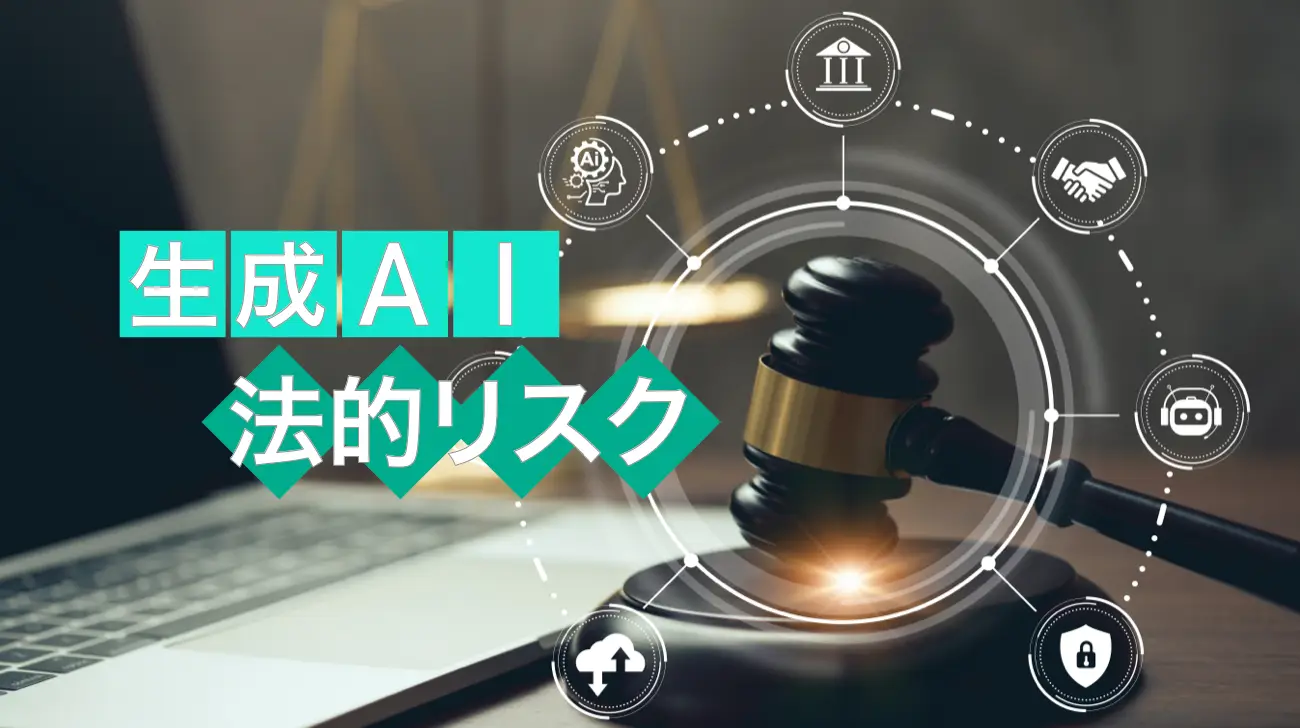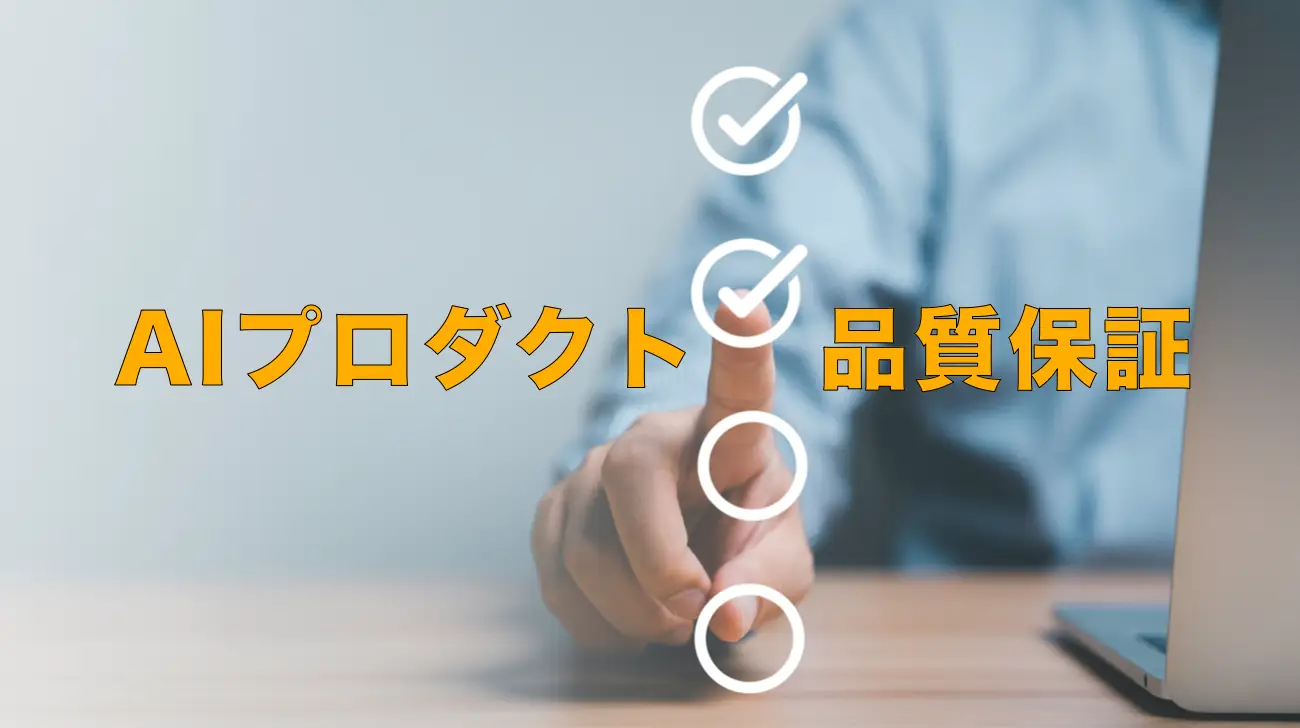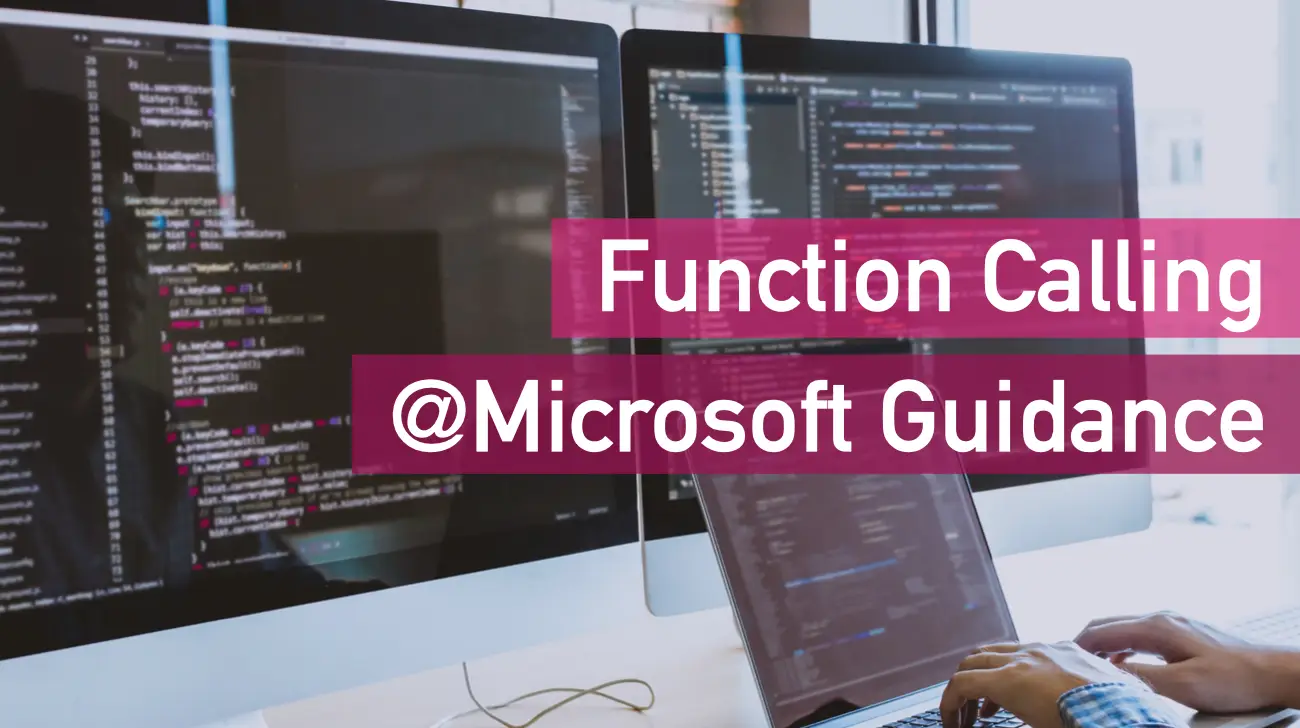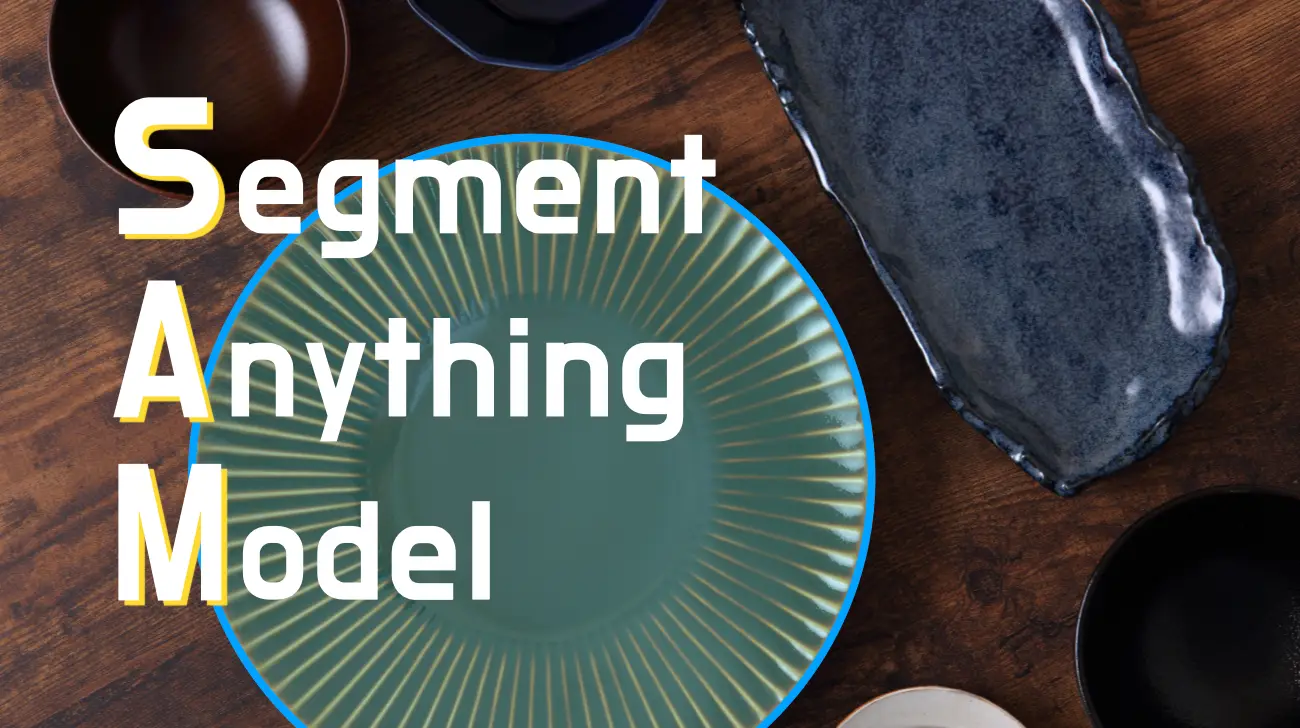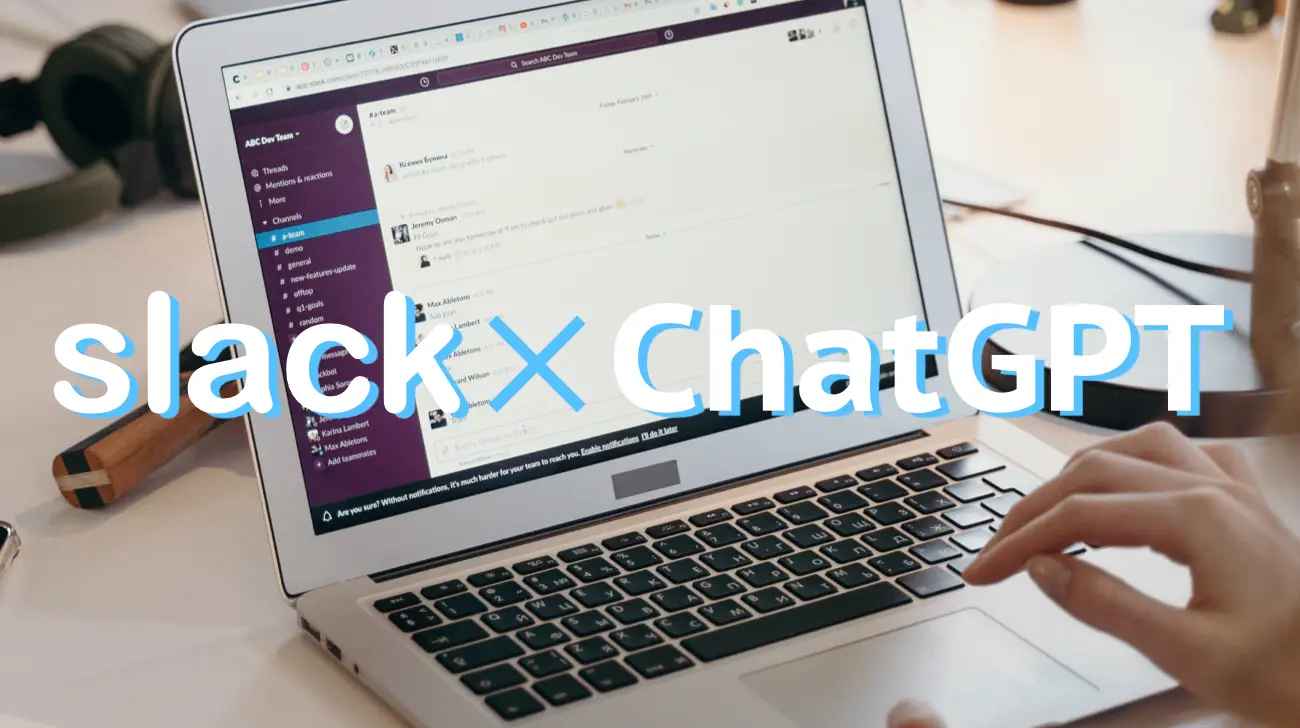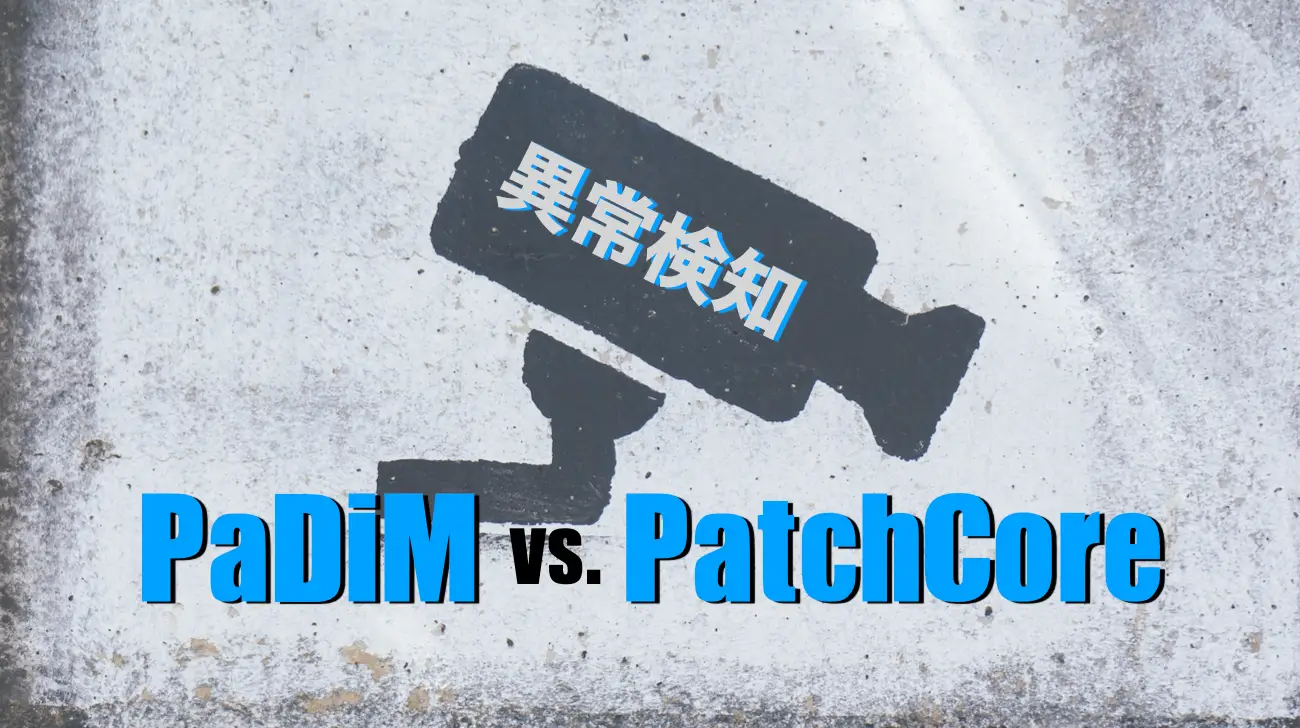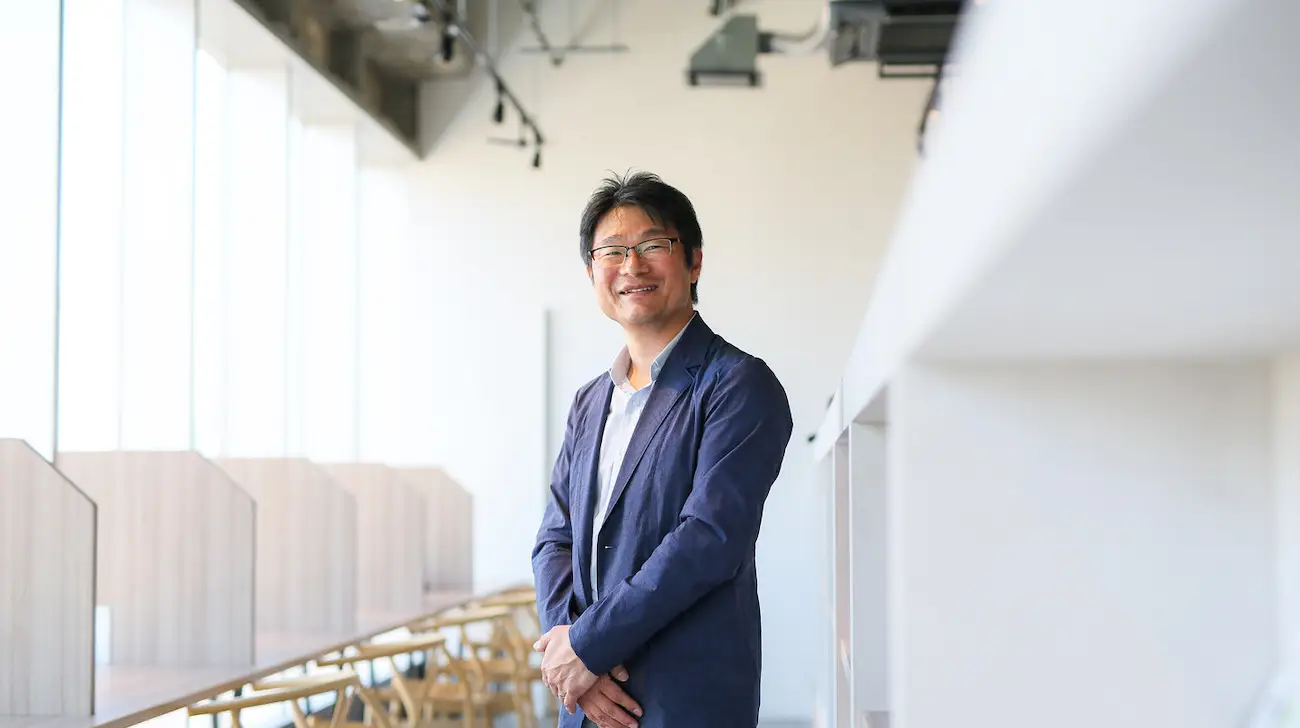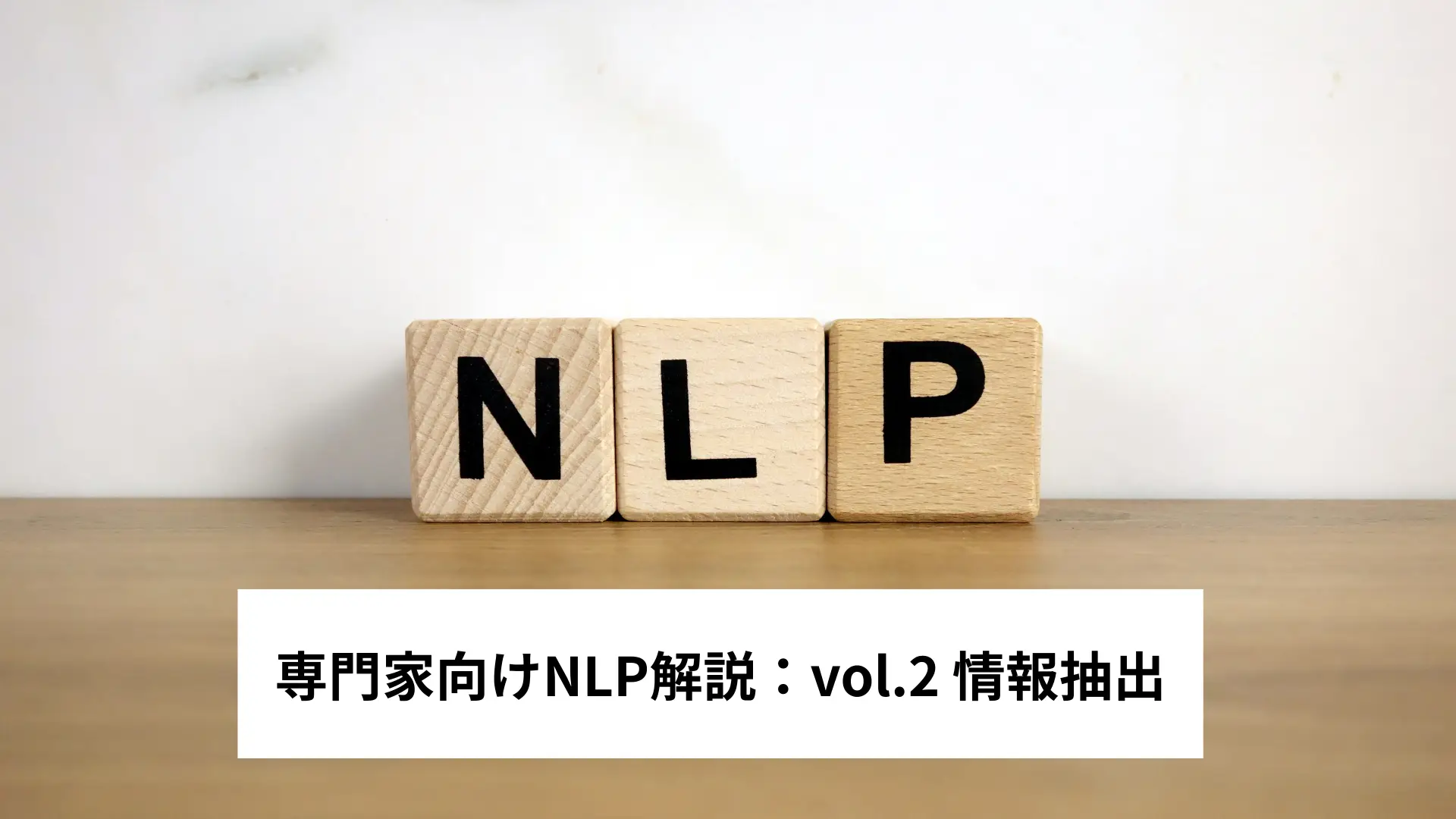
Behind the Product 〜 生成AIを使った製品開発の舞台裏

昨年、正式に提供が開始した調和技研初のSaaSプロダクトである生成AIチャット
ツール『AIWEO (アイウェオ) for ヘルプデスク』(以下、AIWEO)ですが、
リリースからこれまでに多くの企業様にお声がけをいただいています。
単純に製品を使いたいというだけではなく、そのコンセプト・世界観へ興味を
持っていただくケースも多く、大変うれしい限りです。
今回はそのAIWEOについて、もっと多くのお客様に知っていただきたく、その開発
に至ったストーリーやコンセプト、 今後のサービス展望などについて、AIWEOの
生みの親であるキーパーソンに話を聞いてみました。
今回インタビューしたキーパーソンはこの2名です。

(右)武藤 悠貴(ビジネス開発部 事業推進G マネージャー)
(左)中田 侑輝(研究開発部 プロダクト&エンジニアリングG リーダー)
AIWEO誕生(リリースに至った経緯)
Q. まずはじめに、このAIWEOをリリースするに至った経緯について教えてください。
武藤)
調和技研としてSaaSプロダクトへの取り組みを本格的に始めたのは、2024年の年明け頃で
した。プロダクト開発を検討するにあたり、その投資効率を上げるために「顧客へのソリューション提供」で得たナレッジを転用して開発・推進することを意識しており、私はちょうど「ブランド名をつける」タイミングで入社し、プロダクトチームの推進リーダーとなりました。
皆さんまだ記憶に新しいと思いますが、当時国内では「生成AI」は流行語になるほどの注目を集めており、もともと多数のAIモデル開発を受託していた弊社にも、非常に多くの企業様からお問い合わせをいただいていたようです。
そんな世界的に気運が高まる中でスタートした取り組みですが、すでに他社プロダクトが多数輩出されているタイミングでしたので、どんな製品を出すのかも含めて非常に悩んだ記憶があります。なにせ弊社としてもSaaSプロダクトへのチャレンジは初めてでしたし、一方で目の前では広がっていく市場があるわけです。いろんな考えは巡ったのですが、私の所属する事業推進グループは会社の成長を中長期的に持続・加速させるための推進役でもあるため、AIWEOを商材としてのポジショニングを明確にしながら、「当社のビジネス全体に好影響のあるプロダクト」としていきたいと思うようになり、プロダクトを世に送り出すことを決めました。
AIWEOの優れた点
Q. 世間にはたくさんの生成AIプロダクトがありますが、AIWEOが他社と比較して優れている点はどこでしょう?
武藤)
シンプルに、人間にとっての身近さや親近感である点は負けないと思っています。
AIWEOは、調和技研という技術立脚の企業で、あえて製品づくりにデザインを強く取り込んでいるのが特徴です。メカメカしい要素ではなく、触れやすい色味や形、キャラクター要素を取り入れることで、生成AIに興味がある人だけではなく、「気になっている人たち」にもAIWEOに触れてもらえるように設計しました。
人間どうしても、こうしたAIはじめ、わからないモノ・技術に対して心を寄せられない、興味を持てないと思う方も多いと思います。この感情は、製品づくりにおけるデザイン的な考え方が取り込まれていないことで生まれている弊害だと考えており、AIWEOでは“親近感”をきちんと醸成でき、私たち人間が「使いたい」と思うサービスづくりをしています。
ただ反面、こうした打ち出しだけで活用はなかなかうまくいかない、一筋縄ではいかないということも十分理解しています。実際、市場を見てみると、一昨年(2023年)は「とりあえずサービスを使え」の風潮で企業様も生成AIの社内導入を進めていました。2024年半ば以降は、少し慎重な企業が増えている印象でしたし、アーリーマジョリティ(長期的な活用を視野に入れた検討・導入をしようという考え)の声に変わってきていると思います。
Q. 実際に生成AIの利活用に苦労している企業様の話をよく聞きますよね。AIWEOでも取り組んでいることはありますか?
武藤)
そうですね、市場変化に伴い「(使う従業員の)リテラシーはどうするんだ?」とか、「いくら人間が使いやすいと言っても限界はあるよね」といった声もありました。実際、製品上でどれだけ使いやすくできたとしても、利活用促進の観点からは老若男女をすべてカバーできるわけではないですし、どう受け入れていってもらうかについてはかなり悩みました。幸い、弊社はAI人材の育成についても経験値があったため、こういったノウハウを用いながらご利用いただくお客様へ、生成AIを活用できる人材の育成を支援するサービスを提供することを思いついたんですよね。
ですが、人材に活用方法を教えれば課題解決かといえばそういうわけではなくて、利用する側の視点としては「企業としてどんな活用が歓迎され、どんな使われ方は非推奨なのか」ということが気になるわけです。あわせて調査をすると、多くの企業で利活用のガイドラインが整備されていないこともわかってきました。こういった市況感から、AIWEOでは企業全体のガイドラインを整備しながら、利活用する人材も育てられるパッケージもご用意をしています。
ガイドラインについては少し思っていることがあり、実は検索をしてみるとテンプレートがたくさんあるんですよね。そういったものを流用すればいいじゃないかという声もあるのですが、そうしたテンプレートのほとんどは『生成AI利用の注意』に留まっていて、社内活用・促進の観点ではないんです。
実際、ガイドライン整備で重要なのは、企業としてどのように生成AIを活用していきたいかということの宣言、あるいはそれが企業戦略・事業戦略や人材戦略にどう紐づいているのかという部分です。こういった部分をきちんと戦略的に明文化することが、先端的な技術を能動的に利活用してもらう上で特に重要だと考えています。
調和技研はこれまでAIを企業現場で使ってもらえるように設計してきた実績やノウハウが多数あります。そうした背景があるからこそ、このような経験値を使ってお客様の製品・サービス利用をサポートできるのですが、これは調和技研ならではの特徴ですね。
企画・製品化する上で一番大切にしたこと
Q. AIWEOを企画・製品化する上で、一番大切にした面はどこでしたか?他社競合と比べ、製品イメージとして登場するキャラクターやサービスページのタッチなど、とても親近感を覚えますが?
武藤)
このAIWEO(アイウェオ)というネーミングは、“人間が親しみやすいサービスづくり”を前提としていることは先ほど言いましたが、考える上では『自社理念』『市場目線』『サービス印象』の視点から、関連しそうなワードを240項目洗い出すところから始めました。240のワードを土台に、自分自身が思いついた単語の組み合わせから50個に絞り、それらをイメージごとにカテゴリ化し、その中から当社のコンセプトに合うものを更に絞り込んで決めています。ブランド名をつけるというのは責任の重いものでしたが、入社して最初の仕事がこれだったこともあり、2週間くらいは悩んだ気がします。
このロゴの可愛らしいキャラクター(ブランドマーク)は、当社の企業名にも入っている“調和”を重視し、AIを取り巻いているロボットのような機械的なイメージを排除することを意識して制作されました。コミュニケーションをイメージするフキダシをベースに、人間とAIが完全には融合せずに溶け合っている様子が描かれています。親しみ要素でこのテイストに寄せていっていたのも事実ですが、実際に他社類似サービスを分析した結果、『親しみのあるポップなデザイン』のロゴが少ないというのもあり、ここでも差別化を図りました。
普段はここまで喋らないのであえて話しておくと、人間とAIがお互いに見つめ合っている様子は、どちらかがどちらかを使うのではなく、両者が歩み寄って共に両存在にとってよい未来を実現する。そんな願いを込めています。

サービスの側面で話をするなら、やはりAIWEOは比較的後発ではあったので、競争に巻き込まれること自体が大きなビジネスリスクになると考え、「比較されないこと」を目指してプロダクトデザインしましたね。先日新聞の取材を受けた「なりきりAIWEO」や「バトンタッチ」など、他社サービスにはない独特の機能があります。
こういった製品づくりを支えるのはもちろん最高のプロダクトチームでして、ビジネスとエンジニアリングとデザインをバランスよく判断できる私と、事例のないものをデザインするブランドクリエイター、システム設計を支えるスーパーエンジニアたちで構成されています。
Q. では今の質問を、開発という側面から質問します。中田さんが技術側の責任者として、このAIWEOについて一番重視した点は何ですか?
中田)
私が一番重要視したのは、これまで生成AIを使った経験がない方、もしくはなんとなく知ってはいるけれどビジネスでの活用経験がないという方をペルソナとした設計・開発をすることでした。
生成AIという技術・サービスは、国内においてもある程度認知はされており、ビジネスレベルとまではいかなくても、個人レベルで無料版を中心に利用されている人は結構いらっしゃいます。
しかし、圧倒的に使ったことがない方のほうが多い中で、なるべく技術用語を表に出さないようにして、AIWEOの世界でマスク(橋渡し)する点を意識して開発しました。
例えばChatGPTを使う場合、使用するモデルの選択などをユーザー側で決定しなければなりませんが、そうした違いがわかりづらい部分をダイレクトに提示するのではなく、“賢いAIWEO”など、キャラクターで選択してもらうといった形で、初めて利用する人の抵抗感の敷居を下げることがユーザビリティ向上には大切であると意識しました。
その一例として、生成AIでよく耳にする『LLM』と『RAG』。このそれぞれの意味は調べれば理解できますが、いざ実際に生成AIを使う段階になると、ふと忘れてしまったり、それが何であったかをその都度調べ直したりと、使う前から煩わしく感じてしまう人も多くいます。

そうした初心者の方が感じる煩わしさを少しでも解消できるよう、AIWEOではLLMモードとRAGモードの切り替えをユーザーで選べるようになっています。
LLMモードでは、「とりあえずAIWEOと話してみる」というように、気軽に使ってもらえるよう工夫しています。RAGについては、『AIWEO社内コンシェルジュ』というネーミングを付けており、RAGという言葉を意識しないようにしています。
AIWEOをよりユーザーフレンドリーに
Q. リリースから半年が経過した今、リリース当初から多くのお客様にご利用いただいていることは、調和技研としても非常に嬉しいかぎりですが、機能バージョンアップをされましたが、それはどんな機能なのでしょうか?
中田)
つい先日、AIWEOをご利用いただく際にお客様に選んでいただくプランに追加がありました。この追加は、昨年12月にAIWEOをリリースして以降、嬉しいことにたくさんの企業様からご興味をお持ちいただくことができた中で「ご利用いただくユーザー数(社員数)をもっと多くできないか」という課題があり、それをカバーするためのプラン追加をおこないました。
その追加された新プランをご利用のお客様が使えるものとして、AI(AIWEO)が回答できなかったときに、人間にバトンタッチする機能を追加しました。
答えられなかった質問を社内ヘルプデスク担当に引き継ぐことで、正確な情報を提供・取得できますし、その回答はAIWEOが学習し、以後同様・類似の質問をしてくるユーザーへは自動回答します。こうした“業務設計を意識したAIからの引き継ぎ機能”は、他社類似製品にはないものです。
それと、これは全プラン共通で新たに加わった機能として『なりきりAIWEO』というものがあります。生成AIを利用する人の多くが、「自分では思いつかない」「ご自身の専門領域ではない世界の情報を得たい」と考える場面が結構あると思いますが、こうした情報を取得するにはちょっとしたコツが必要だったりします。
このコツを手軽に使えるようにと搭載したのが『なりきりAIWEO』です。ユーザーは、自分が知りたい情報を持った個性豊かなAIWEOを選ぶことで、専門的な観点で質問に答えてくれます。ちなみにこの専門家は、お客様の社内・業務に特化した“専門家AIWEO”としてカスタマイズすることができますので、業務効率化のお手伝いができると思います。
二人にとってAIWEOとは
Q. 最後に。お二人にとって、このAIWEOはどんな存在ですか?

武藤)
私が名付け親でもあるためAIWEOは我が子のような存在です。AIWEOがどのように成長していくのか、どんな人達と接して、どんな関わり方をしていくのかとても楽しみですし、その可能性にとてもワクワクしています。それと同時にAIWEOが人間社会におけるAIへの不安を少しでも払拭できるよう、一緒に取り組んでいきたいですね。
中田)
一言で言うと、AIWEOは私にとって『共に歩む仲間』ですね。使っていただくユーザーのお役に立てるよう、切磋琢磨していく仲間ですし、このAIWEOが仕事・創造に貢献できる、より人間に近しい存在に将来なれると私は信じていますし、そうなることを願って、これからも自分の仕事に全力で取り組んでいきたいと考えています。
【AIWEO for ヘルプデスクに関する各種情報】